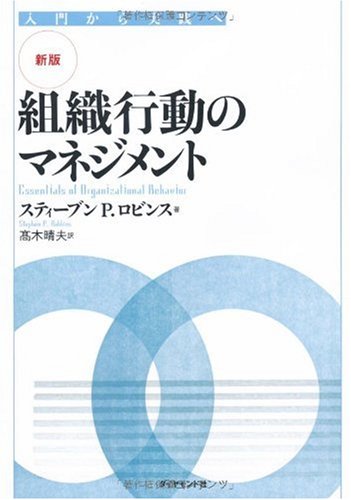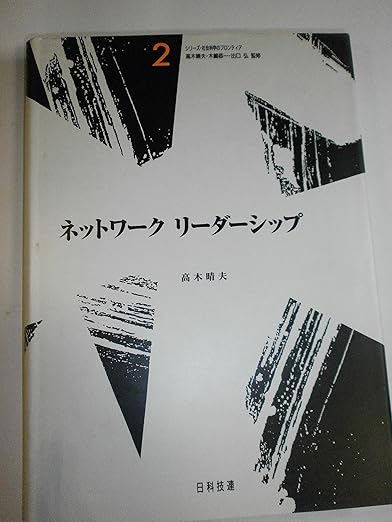良質な問いで、組織をじっくり育てる。〜ビズクリサポーターの支援事例・竹中千恵〜


竹中 千恵 たけなかちえ
一見、良好な経営状況の裏で抱えていた課題
今回ご紹介いただく支援事例について教えてください。

今回私が取り上げるのは、年商10億円ほどのメーカーさまとの事例です。社長と経営幹部のリーダーシップのもと、社員の方はみな真面目に仕事に取り組んでいます。業績も決して悪くない、トラブルが起こったときには当たり前のように部署の垣根を超えてサポートする、そんな組織です。
一見、経営状況は良好に見えますが、そんな企業でも課題はあったんですね。

はい。もともと中期経営計画は存在していたんですが、ビジョンと経営戦略がありませんでした。「中期経営計画を、どのように現場に落とし込んでいけばいいのか」という観点からのアドバイスを求められていて、私が支援することになりました。
ビジョンと戦略がなくて中期経営計画だけがある状態では、どうして不十分なのでしょうか?

「中期経営計画はあるけれど、ビジョンと戦略がつくられていない」という状態だと、組織として目指すベクトルが不明確になってしまいます。そうなると、「どのようにPDCAを回すと組織を進化させられるか」といった観点が抜け落ちてしまい、気づいたら同じステージでPDCAを回し続けていて数年経っても進歩していない、という状態になりがちです。
「どんなゴールを設定し、どんなアプローチを取っていくのか」を事前に整理しておくことは、組織を成長させる上でとても重要です。
もともと竹中さん自身は、そのようなビジョンや戦略をつくる支援を行っていたのでしょうか?

もともと私は「経営品質協議会認定セルフアセッサー」という認定資格を保有していて、自己革新し続ける組織づくりの支援を得意としています。ビジョンや戦略を自分たちで考えて事業活動に落とし込み、取り組みを振り返って改善へとつなげていくという習慣をつくるサポートを行っています。

時間をかけて、組織を芯からつくっていく
実際に行った支援のプロセスを具体的に教えていただけますか。

1年目は、ほぼビジョンと戦略づくりに絞りました。まず経営者と経営幹部の皆さんに、3カ月でビジョンと戦略の原形をつくってもらいました。その後、6ヶ月かけてそのビジョンと戦略を深掘りして、納得いくまで練り直したんです。
創業の経緯を振り返るところから始まって、自分たちの強み、外部環境の変化、それを踏まえたありたい姿と戦略、顧客に提供する価値など、さまざまな観点で議論を重ねました。さらに、「ただつくって終わり」にならないよう、成果の指標をどう設定するのかまで、しっかりディスカッションしました。最初に10年後を見据えて方向性を定められたのが、1年目の大きな成果でした。
2年目からはどのような支援を行ったのでしょう?

2年目以降は、将来的に組織を担っていくメンバーの育成も見越して「人づくり」を進めました。まずは、どういう人材を育てていくのか、組織や人の能力をどう高めていくのかを綿密に考えたあと、次世代のリーダー人材をプロジェクトメンバーに迎え入れました。そして、現社長・幹部、そして次世代リーダーとともにビジョンと戦略を練り直したり、現場マネジメントに落とし込んだりといった取り組みを3年ほどかけて行ってきました。
今は、約4年の取り組みの中で、何ができて何ができなかったのか、これからどうしていくのかを振り返りながら、組織全体にビジョンと戦略の浸透を図っているところです。
支援は対面で行ったのでしょうか?

実は基本的にオンラインなんです。遠く離れたところにある企業なので、最初の1、2回は訪問しましたが、それ以外の支援は、ほぼ全てオンラインで行っています。
オンラインで、経営支援を行うのは難しくはないのでしょうか?

1、2回訪問して組織の雰囲気や社員さんのキャラクターなどがわかれば、ビジョンと戦略の策定自体はオンラインでも差し支えなかったです。また、私は「ホワイトボード・ミーティング®」という、ファシリテーションの認定資格を持っています。オンラインで画面共有して、リアルタイムで可視化していくことで、スムーズに支援を行うことができたと思います。
次世代の担い手が生まれつつある手応え
5年間の支援を経て、現在の手応えはいかがですか?

社長の息子さんが後継者に決まったことが大きな転機だったと思います。現経営陣と後継者、それを支える次世代リーダー人材人材とのコミュニケーション機会を多くとることで、次世代リーダーに「自分達の時代が来たんだ」という自覚を芽生えさせることができました。現経営陣と次世代リーダー人材とのコミュニケーション機会を多く取ることで、現社長の「跡継ぎをどうしよう」という不安を解消しつつ、次世代リーダーに「自分たちの時代が来たんだ」という自覚を芽生えさせることができました。
世代交代の目処を立てることができたんですね。

ただ、次世代リーダー人材の中でも温度差があり、会社づくりが好きな方と現場でプレイヤーでいたい方に分かれたのも事実です。この経営改革プロジェクトでは、当初次世代リーダー人材のメンバーは4人いましたが、最終的に残ったのは2人だけでした。ただ、組織づくりにおいて、この過程は必要だと考えています。「船頭多くして船山に上る」ではありませんが、全員が全員、経営幹部になる必要はありません。会社経営にフィットする人が自然と選抜されて、組織を担う立場になっていく方が自然ですから。
今後の計画はいかがでしょうか?

次世代の幹部候補たちが、自分たちで練り上げたビジョンと戦略に則ってPDCAを回せるようになることが今の目標です。そうすると、組織のレベルがもう一段階レベルアップすると思っています。
ただ、今のフェーズはまだ折り返し地点です。新たなカルチャーが組織に宿るまで、これからの5年間で一緒に何ができるかを考えながら伴走していこうと考えています。

「これが私の支援スタイル」
経営支援を行うにあたって、竹中さんが最も大切にしていることは何でしょうか?

「良質な問いを立てる」ということですね。どのような問いを立てると、一番深く考えてもらうことができるのかを常に意識しています。
経営には、絶対的な正解はありません。その中で必要になるのが「自分たちはどういう価値観のもと、どういう経営判断をしていくのか」という視点です。そんな視点を養うには、問いに対して自分の頭で考え続けることしかありません。私は、経営者の皆さんが自分自身で考えて、実践できるよう、良質な問いを提供して自走するサポートを行っています。
最後に、竹中さんの支援はどのような企業にフィットすると思いますか?

「いい会社をつくりたい」という想いを持った経営者にフィットするのではないかと思います。目先の利益だけではなく長い目で見て組織のあり方を考えたいという方、取り組みを振り返っていい組織習慣をつくりたい方などは相性がよいのではないかと思います。長期的なお付き合いをしながら、よりよい会社づくりに伴走できれば幸いです。
【竹中千恵のおすすめ書籍】
『【新版】組織行動のマネジメントー入門から実践へー』スティーブン P.ロビンス著、 髙木 晴夫 訳
『ネットワークリーダーシップ』高木 晴夫著
私の大学院時代の恩師の本です。組織行動や組織開発の分野において非常に示唆に富んだ内容で、人づくり、組織づくりに関心がある方にはぜひ読んでいただきたいです。